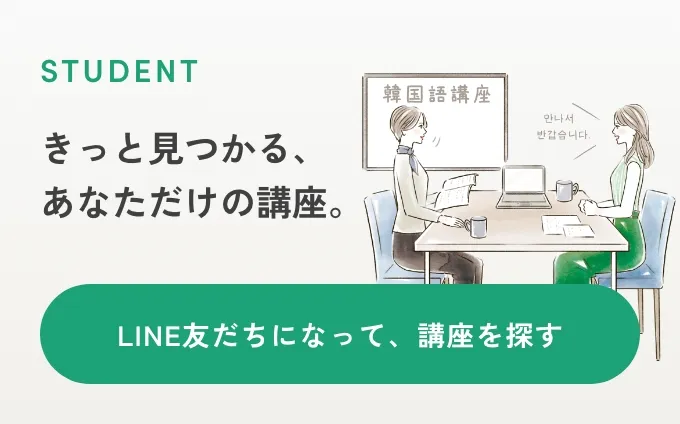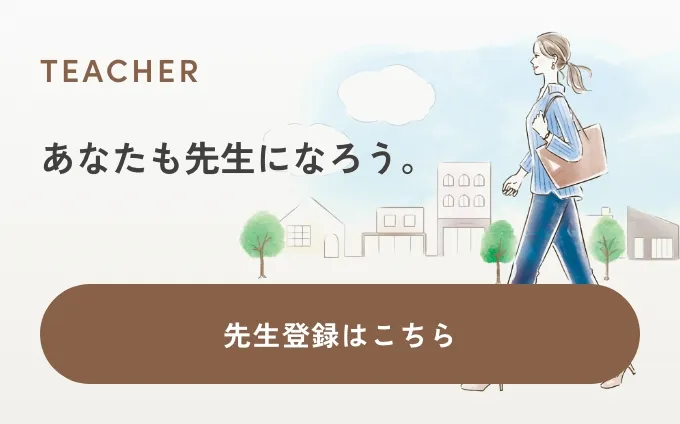部活動の地域移行はいつから?見えてきた課題とモデルを調査

現在、部活動の地域移行が話題になっています。学校生活のシステムが大きく変化するため、多くの教育関係者は頭を抱えているようです。部活動の地域移行はいったいいつから始まるのか、メリットは何なのか、問題や課題はないのかなど、さまざまな疑問点が存在します。この記事では、部活動の地域移行に関する基礎情報をご紹介します。現時点で予想できる課題点や理想的なモデルについても触れるため、ぜひご覧ください。
部活動の地域移行とは?いつから始まる?
部活動の地域移行は、スポーツ庁がすすめる教育施策の一つです。公立中学校の部活動指導を、教師ではなく地域の指導者に行ってもらう施策であり、スポーツ系だけではなく、文科系の部活も含みます。なお、私立中学校や高校での部活動は含まれません。私立中学校は学校ごとの教育方針が異なり、高校は義務教育ではないからです。
開始のタイミング
少しずつ対応学校を増やしていくため、始まるタイミングは学校によって異なるでしょう。現在も、段階的に導入している学校は存在します。ゴールとしては、2025年までに休日、それ以降は平日も完全移行することが目標です。2023年度以降の3年間を「改革集中期間」に定めて、全国的な施策を行う予定となっています。
教員の負担軽減
この施策が始まった背景には、教員の働き方改革が関係しています。現代社会において、教師の労働環境の悪さは大きな問題です。残業時間が大幅に増えており、部活動まで担当するとほぼ休みがない状態です。
部活動の試合は基本的に土日に行われるため、指導や引率のための休日出勤が求められます。教師を志望する若者が減っている一因にもなっており、迅速な対応が必要です。この対策の一環として、部活動を地域移行することで、負担軽減を図っています。
部活動の少人数化
なお、少子化による部活動の少人数化も理由の一つです。生徒数そのものが減少しているため、各部活にも人が集まらなくなっています。特に、人数が固定されているサッカーや野球などの団体競技では、この問題は深刻です。施策上では、「複数の中学校が集まって指導を受けること」も望ましいとされているため、これで部活動の少人数化もカバーできるでしょう。
教育の質の向上
また、教員の負担が軽減されると、教育の質が上がることも期待されています。部活動の地域移行には、複数のメリットがあるということです。教育のあり方に関して、より詳しい情報を知りたい人は下記の記事を参考にしてください。
現時点で予想できる課題点・問題点

部活動の地域移行は非常に価値のある施策ですが、現時点で課題も多数想定されます。
財源確保
まず、財源の確保が難しい点です。地域指導者に支払う報酬が用意できない地域も多いと予想されます。教師なら給与の範囲内で対応できましたが、別途指導者を用意する場合はそうはいきません。
特に全体的な人口が少ない地域などは、そもそも地域指導者を用意すること自体が難しい場合もあります。子どもが少ない地域は、グラウンドや体育館といった施設も用意できないでしょう。
家庭の負担大
また、家庭の負担が大きくなる点も課題の一つです。複数の中学校が合同で練習を行うことになった際、練習場所まで距離がある生徒も出てくるでしょう。その場合、送り迎えを家庭にお願いする可能性が高いです。
スポーツクラブを利用する場合は、会費を払うこともあるかもしれません。あまりに家庭の負担が大きくなると、家計に余裕がない家庭の子どもが、部活動を諦めるおそれもあります。全国の子どもが平等に部活動を楽しめるように、国の細やかな支援が必要です。
「教える」スキル不足
なお、地域指導者が教育そのものを学んでいないことも大きな問題点です。事故や生徒同士のトラブルなど、イレギュラーな事態が起こったときに、上手く指導が進められない場合も考えられます。さまざまな事態を考慮しながら指導を行わなければならないので、指導者の心身の負担にも気を遣う必要があるでしょう。体罰やセクハラなどのハラスメント対策にも、力を入れなければなりません。
部活動の地域移行を成功させるには、「教える人材」の充実化が必須となりそうです。稼げる「教える人材」になるための方法が知りたい人は、「教え上手は稼げる!」の記事をご覧ください。
理想的な地域移行のモデルについてご紹介
それでは、理想的な地域移行のモデルとは、いったいどんな形なのでしょうか。
モデル校の状態はおおむね良好
現在、すでにモデル校として活動を進めている学校では、現役選手や元プロの選手などが指導者を務めることもあるようです。スポーツの専門家だからこそ教えられるテクニックや、実践的な戦術を学べるため、生徒からの評価は高い様子です。
学校の先生とは違う立場で生徒と触れ合えることで、先生には話せない内容を相談できるというメリットもあります。もちろん資金繰りの問題など課題はありますが、試行錯誤しながら、一つずつクリアしていこうとする前向きな学校が目立ちます。スムーズな運用システムが地域格差なしで確立できれば、部活動の地域移行はさまざまな問題を解決するでしょう。
「教える人材」が必要になる
しかし、これから全国的に制度が広がるとなると、より多くの「教える人材」が求められます。生徒一人ひとりに寄り添った指導を実現するために、人材の増加は必要不可欠です。今、社会貢献のための教育起業なども注目されていることからも、それはうかがえます。自分が得意なものを人に教えることは、社会貢献につながることになります。「誰かに自分のスキルを教えたい」と考えている人は、行動に移すことをおすすめします。あなたのスキルが、日本の未来を助けるかもしれません。
社会貢献に関する参考ページはこちらです。教育が社会にもたらす利点について知りたい人は、下記の記事を参考にしてください。
「おけいこタウン」で社会貢献しよう

部活動の地域移行は、教育の品質を上げるためにも必要な施策だということがわかりました。まだ問題は山積みですが、時代の流れに沿って、制度が整うことを期待しましょう。そして、少しでも子どもたちの教育を充実化させるためには、「教える人材」の拡充が必要です。スキルを持つ人材が増えると、未来の教育がよりよく生まれ変わるでしょう。
教育によって社会貢献をしたいと考えている人には、 おけいこタウンをおすすめします。 おけいこタウン とは、習い事のマッチングプラットフォームです。スキルを誰かに教えたい先生と、スキルを身に付けたい生徒を結びつけます。
スキルのジャンルは、ハンドメイドからビジネススキルまで多種多様です。今積んだ経験が、いつか部活動の地域移行でも役に立つかもしれません。講座開催場所の提供や集客サポートなど、初心者でも気軽に講座を始められるシステムが整っています。自分のスキルを社会貢献に活かしたい人は、ぜひ おけいこタウン の公式サイトをご覧ください。