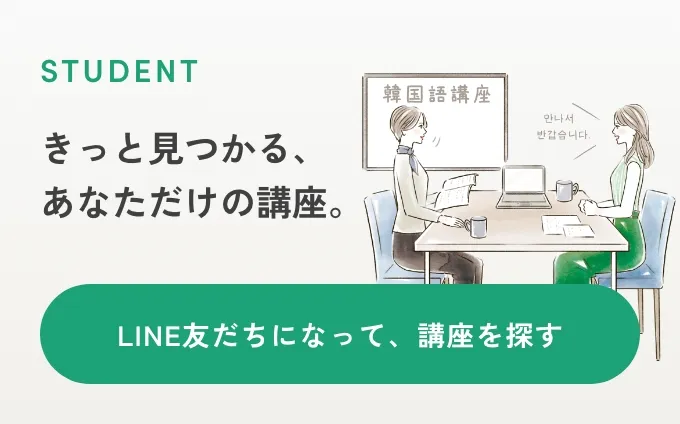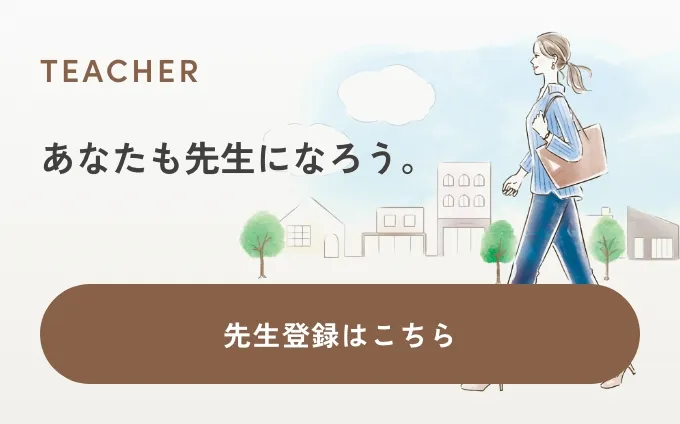個人事業主におすすめの保険は?備えるべきリスクもあわせて解説
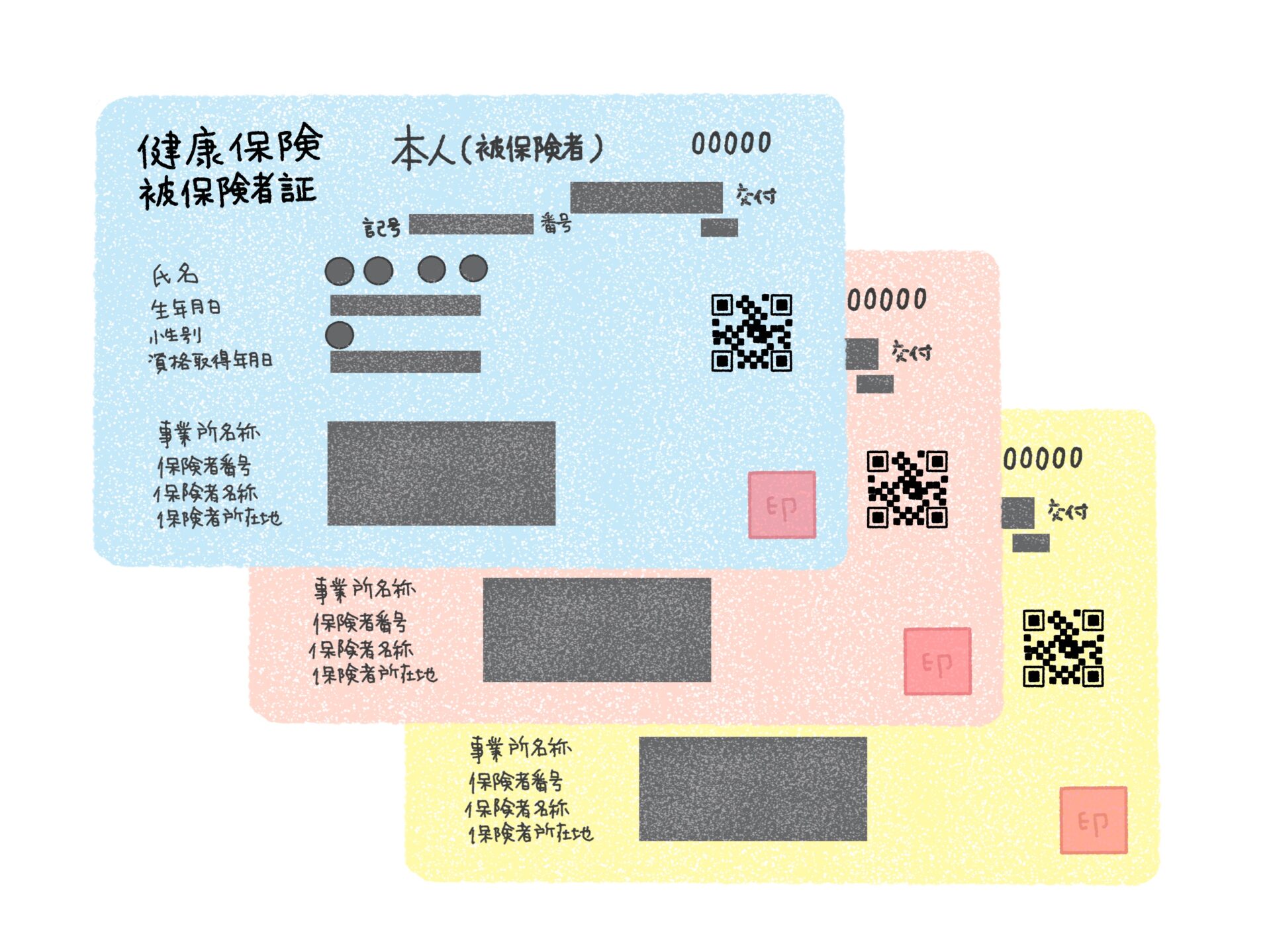
個人事業主として独立した人は、どのような保険に加入すべきか迷っているのではないでしょうか。個人事業主は会社員と比べて、利用できる公的保険制度が限られているため、不足している保障を民間の保険で補う必要があります。本記事では、個人事業主が備えるべきリスクとおすすめの保険をご紹介しますので、参考にしてください。
個人事業主と会社員の社会保険を比較
会社員と個人事業主の社会保険の違いは以下のとおりです。
|
社会保険の種別 |
会社員 |
個人事業主 |
|
医療保険 |
健康保険 |
国民健康保険 |
|
年金保険 |
厚生年金 |
国民年金 |
|
介護保険 |
40歳以上で加入 |
40歳以上で加入 |
|
雇用保険 |
制度あり |
制度なし |
|
労災保険 |
制度あり |
制度なし |
個人事業主が意識しておきたい箇所は、健康保険ではなく国民健康保険である点と、厚生年金ではなく国民年金(基礎年金のみ)である点です。特に健康保険の「傷病手当金」は、病気やケガで働けなくなった場合でも、給与(標準報酬月額)の2/3が手当金として支給される頼もしい制度だったので、個人事業主になっても同様の保障を用意しておくことをおすすめします。
個人事業主の社会保険については下記の記事で詳しく解説しますので、気になる人はそちらをご参照ください。
個人事業主の社会保険ってどうするの?仕組や加入方法についてわかりやすく解説
個人事業主・フリーランスに保険加入をおすすめする理由とは
個人事業主・フリーランスに保険加入をおすすめする理由は、国民健康保険や国民年金などは、会社員と比較すると保障内容が不足しているからです。傷病手当金の代わりに、働けなくなった場合に備えて保障を準備することや、老後の生活資金に上乗せできる私的年金を準備しておきましょう。
ここからは、個人事業主が備えるべきリスクについて詳しく解説します。
病気やケガにより生活資金が不足するリスクがある
個人事業主のリスクとして最も意識しておきたいことは、病気やケガで働けなくなるリスクです。先述したとおり、会社員の健康保険であれば、病気やケガで働けなくなったとしても、休業している間も給与(標準報酬月額)の2/3が傷病手当金として支給されます。
しかし、個人事業主の国民健康保険では、病気やケガで働けない場合は公的制度による保障がないので、貯蓄等の予備資金で収入を補うしかありません。
老後の生活資金が不足するリスク
個人事業主は、厚生年金ではなく国民年金(基礎年金部分のみ)なので、老後の生活資金が不足するリスクもあります。厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和2年度の老齢年金は月額14.6万円支給させていますが、国民年金は月額5.6万円のみの支給とされています。
国民年金だけでは老齢年金の支給額が少なくなってしまうので、iDeCoや国民年金基金、個人年金保険等を活用して老後資金の準備も意識しましょう。
死亡または障害を負うリスク
老後資金と同様に、遺族年金や障害年金も厚生年金ではなく基礎年金となります。基礎年金部分のみの支給では、自分にもしものことがあった場合、残された家族の生活費が不足するかもしれません。
遺族基礎年金の年金額は令和4年4月現在では以下の金額となっています。
子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+子の加算額
子が受け取るとき
(※次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
777,800円+2人目以降の子の加算額
- 1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
- 3人目以降の子の加算額 各74,600円
残された家族へ充分な生活費を残したいのであれば、不足分を補う目的で保険に加入しておくことをおすすめします。保険金額は、自分の子が独立するまでの生活費を目安とするといいでしょう。
個人事業主・フリーランスにおすすめの保険を6つご紹介

ここからは、個人事業主・フリーランスにおすすめの保険を6つご紹介します。それぞれの目的ごとに保険の内容を解説しておりますので、参考にしてください。
所得補償保険・就業不能保険|病気やケガで働けなくなったときの保険
個人事業主になってまず加入しておきたい保険は、病気やケガで働けなくなるリスクに備える「所得補償保険」と「就業不能保険」です。自身の収入に合わせて受け取る保険金を設定して、約款(保険の契約内容)所定の働けない状態になった場合に該当すると、収入の代わりとして保険金が毎月受け取れる保険です。
2つの保険の違いは、「損害保険か生命保険か」という点と、免責期間(働けなくなってから保険金が受け取れるようになるまでの待機期間)に違いがあります。
おすすめは損害保険の所得補償保険で、その理由は、免責期間が4日や7日など短期間であるため、働けなくなった場合の収入減少にすぐ対応できるからです。ただし、保険期間が1年と短いため、一時的な収入の補てんにしかならない点には注意が必要です。免責期間よりも保険期間に魅力を感じるのであれば、就業不能保険をおすすめします。
所得補償保険と就業不能保険の特徴や違いは以下のとおりです。
|
|
所得補償保険 |
就業不能保険 |
|
保険の種類 |
損害保険 |
生命保険 |
|
保険期間 |
1年など限られた期間 |
60歳など一定の年齢まで |
|
免責期間 |
4日や7日など短期 |
60日、180日など長期 |
|
保険金額 |
契約前12か月間の所得の50〜80%が上限 |
契約前の年収に応じた上限額 |
※保険会社によって条件が異なる場合もあります。
定期保険・収入保障保険|家族の生活を守る保険
自分にもしものことがあった場合に、残された家族の生活を守るための保険として、「定期保険」と「収入保障保険」をおすすめします。自分が死亡もしくは介護状態(定期保険の場合は特約)になった場合に保険金が支払われる保険です。
定期保険や収入保障保険は、終身保険のように解約返戻金が大きいわけではないので、比較的安い保険料で大きな保険金を残せることが特徴です。2つの保険の違いは、保険金を一括で受け取るか、給料のように保険金を毎月受け取るかの違いです。
一般的に、定期保険は一時金として、収入保障保険は年金形式で受け取ります。収入保障保険も一時金受け取りを選択できますが、その場合は年金形式での受取額より少なくなります。
医療保険|病気やケガによる出費を減らす保険
個人事業主は収入が不安定なので、大きな支出はできるだけ避けたいと感じる人が多いのではないでしょうか。入院や手術、ガン診断や八大疾病による治療費の支出をおさえられることが医療保険の特徴です。
生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」によると、平均入院日数は15.7日となっています。そのうち「5〜7日」が27.3%と最も多く、「8〜14日」が27.1%と2番目に多かったです。
また、医療費についてですが、高額療養費制度を利用した人を含めた自己負担の平均額は20.8万円となっています。そのうち、「10〜20万円未満」が30.6%と最も多く、「5〜10万円未満」が25.7%と2番目に多かったです。
医療保険に加入しなくても高額療養費制度があるから大丈夫という意見もありますが、保険料を毎月支払うことで、大きな支出を減らせると考えれば、医療保険の加入を検討してもいいのではないでしょうか。
個人年金保険|老後の生活資金を準備する保険
国民年金では足りない部分を上乗せするために、個人年金を活用する方法もあります。個人年金保険は、満期まで生存していた場合、契約時に設定していた保険金を毎月受け取ることができる保険です。満期までに死亡してしまった場合は解約返戻金を受け取れますが、支払った保険料の総額を下回ることがあるので注意が必要です。
契約時に設定した年齢になると、契約内容に応じて保険金が年金形式で受け取れます。基本的には被保険者が生存している間は年金が受け取れる契約内容になっていて、死亡時は遺族へ年金が支払われることはありませんが、早く亡くなってしまった場合でも遺族に年金が支払われる「確定年金」という種類もあります。
貯蓄が苦手な人や、生命保険料控除の枠を使って節税したいという人におすすめです。節税については下記の記事で詳しく解説していますので、気になる人は参考にしてください。
税金が高いと悩む個人事業主へ!税理士が適切な税金について解説
保険を利用して社会保険の不足分を補おう

ここまで個人事業主・フリーランスが備えるべきリスクと対策として加入すべき保険について解説しました。個人事業主は会社員と違って公的保障が不足しているので、補える部分については民間の保険で補うことをおすすめします。
特に働けなくなるリスクに備えられる所得補償保険は、4〜7日の短い免責期間で保険金を受け取れるので、収入を補てんする手段としておすすめの保険です。 おけいこタウンでは、この他にも個人事業主に役立つ記事を多数掲載しているので、気になる記事があれば参考にしてください。
【監修者プロフィール】
竹中啓倫(税理士・米国税理士・認定心理士)
上場企業の経理として勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表としても活動中。M&Aなどの事業再編を得意としており、セミナーや研修会の講師としても登壇。医療分野にも造詣が深く、心理カウンセラーとして自ら、心の悩みにも答えている。